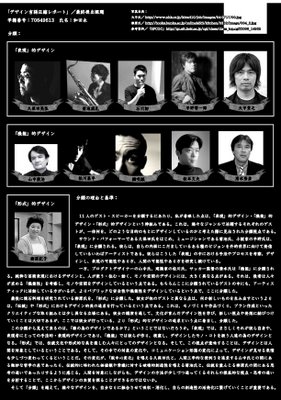
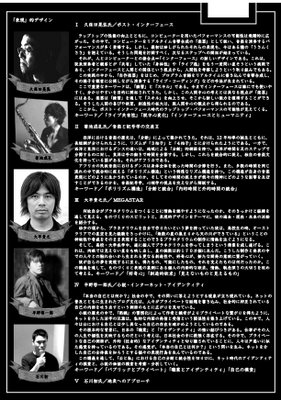

Ⅰ 久保田晃弘氏/ポスト・インターフェース時代のラップトップパフォーマンス
ラップトップの性能の向上とともに、コンピューターを用いたパフォーマンスの可能性は飛躍的に広がった。その中で、コンピューターをリアルタイム音響合成の「楽器」として扱い、音楽を演奏するパフォーマンスが多く登場する。しかし、最初は珍しがられたそれらの表現も、今はある種の「うさんくささ」を抱えている。そうした問題を打開すべく、次なるステップへの開拓が始まっている。
それが、人とコンピューターとの接合点=「インターフェース」の新しいデザインである。これは、従来演奏者と観客とが「共有」していた「身体性」や「ライブ感」をもう一度問い直そうという挑戦であり、インターフェースと人間との関係という視点から、人間性を考察しようという取り組みでもある。
この実践の中から、「自作楽器」をはじめ、プログラム言語をリアルタイムに書き込んで音響合成し、その様子を観客に公開しながら演奏する「ライブ・コーディング」などの手法が生まれている。
ここで重要なキーワードは、「練習」と「スキル」である。今までインターフェースは誰にでも使いやすく、分かりやすいを目的に開拓されてきた。しかし、この人間中心の考えとは異なる視点が「楽器」にはある。楽器は「練習」を通して「スキル」を向上させ、そこから新しい能力を獲得することができる。そうした人間の喜びや欲望、創造性の拡大は、脱人間中心の観点から得られるのである。
ここから、ポスト・インターフェース時代のラップトップ・パフォーマンスの可能性が見えてくる。
キーワード/「ライブ共有性」「脱中心変化」「インターフェースとヒューマニティ」
Ⅱ 菊池成孔氏/音楽と記号学の交差Ⅱ
西洋における音楽の歴史は、「分断」によって築かれてきた。それは、12平均率の誕生とともに、長短調が分けられたように、リズムが「3拍子」と「4拍子」とに分けられたようにである。一方で、西洋と東洋におけるダンスの違いは、地域による「分断」的側面を持つ。西洋が時間を足のステップで分節するのに対し、東洋は手の動きで時間を分節する。しかし、これらを統合的に捉え、独自の音楽文化を持っている国がある。それがアフリカである。
アフリカの民族音楽におけるダンスは身体全体を使った時間の分節を行う。また、多数の時間を同じ流れの中で統合的に捉える「ポリリズム構造」という特殊なリズム構造を持つ。この構造が自身の音楽表現にどのように生かされているのか、そしてその時間の捉え方が我々の精神にどのような影響を及ぼすことができるのかを、音楽記号学、心理学の視点を交えながら解説する。
キーワード/「ポリリズム構造」「分断と統合」「内的時間と外的時間の統合」
Ⅲ 大平貴之氏/MEGASTAR
何故自分がプラネタリウムをつくることに情熱を燃やすようになったのか、そのきっかけと経緯を通して見える、ものづくりのスピリットと、表現的デザインをテーマに、彼の過去・現在・未来の活動を紹介する。
幼少の頃から、プラネタリウムを自分で作りたいという夢を持っていた彼は、高校生の時、オーストラリアでの星空を見た経験をきっかけに、「無数の星の集まりから天の川ができている」ということの神秘性や脅威をそのまま表現することのできるプラネタリウムの制作に情熱を注ぐようになる。
そして、高校・大学在学中、遂に個人でプラネタリウムを作ってしまうという偉業を成し遂げる。これは、肉眼では見えない星をも映し出し、星の総数は約170万個に及んだ。こうした制作と発表の中での人々との触れ合いから生まれる更なる創造性や、好奇心が、新たな開発の意欲に繋がっていく。
彼が自らの夢を実現するに至り、得たもの、可能にしたもの、それを支えたものは何だったのか。この講義を通して、ものづくりと表現の裏側にある個人の内面的な欲求、情熱、執念深さの大切さを改めて考える。
キーワード/「好奇心」「創造的欲求」「見えないものと見えるもの」
Ⅳ 平野啓一郎氏/小説-インターネット-アイデンティティ
「本当の自己とは何か?」社会の中で、その問いに答えようとする現象が立ち現れている。ネットの普及とともに生まれたブログ文化は、人々がプライベートな話題を書き込み、社会的に抑圧されている自己の内面を吐き出すという側面のもとに広がりを見せている。
小説の歴史の中で、「黙読」の習慣化によって作者と読者がよりプライベートな繋がりを得たように、ネットを介した活字の氾濫は、私的な内面の発信と受信という関係性を築き上げている。この中で、人々は公における自己とは少し異なった自己の存在を確かめようとしているのである。
その根本的な背景に、日本の「職業」と「アイデンティティ」の強い結びつきがある。仕事がその人の人生や個性を反映するものだという考えは、日本社会の中に根強く存在する。その中で、プライベートな自己の側面が、外的(社会的)なアイデンティティと切り離されていることに、人々は戸惑いに似た感覚を持っているのである。その感覚が、「本当の自己とは何か?」という問いを生み、ネットを介した自己の全体像を知ろうとする個々の表現行為を生んでいるのである。
この講義を通して、「公と私」における自己の分断と統合性を切り口に、ネット時代のアイデンティティの模索と、小説の価値の模索を考察・分析していく。
キーワード/「パブリックとプライベート」「職業とアイデンティティ」「自己の模索」
Ⅴ 石川初氏/地表へのアプローチ
我々が地図を見る時、意識下にあることは「今自分の置かれている位置=現在地」である。地図は、自分と周りとの位置関係を記号
的に表し、身体性の限界に応えるかたちで我々に位置情報を知らせてくれる。しかし、その地図は現実の関係性とは別の次元に存在し
ている。電車の路線図や二次元の地図などは実際の空間的な配置とは異なるであろうし、誰かによって作られた地図には必ず作成者の
意図や、社会的な制度の反映が存在する。これらの別次元の視点を、実際の空間的体験、空間的感覚へと落とし込んで翻訳する必要が
あるわけだ。
一方で、現実の空間と、地図上の空間の二つの認知が相互作用を起こす事で、今までとは違った視点が見えることがある。石川氏は、
こうしたインタラクションによる風景経験の豊かさの表現をテーマに、GPSなどを使った様々な地図の作成に取り組む。その中で、地
形に沿って絵を描くGPSペインティング等を通して、新しい地表へのアプローチを実践し、我々の身体性と知覚に新たな刺激を与える。
キーワード/「情報の記号化」「空間体験と記号とのインタラクション」 「GPSペインティング」
Ⅵ 山中俊治氏/美しいテクノロジーのための実験工房
工学におけるデザインは、常に多くの人からの理解を求められる。その製品を使う人であったり、企業の人であったり。それは必ずしも自分が美しい、作りたいと思うものと結びついているとは限らない。
しかし、自分のデザインによって、「美的なもの」と「機能的なもの」とをうまく融合させ、一般的に広く浸透していくものを生み出したいものだ。
その打開の糸口として山中氏が提案し、取り組んでることは「プロトタイピング」と呼ばれるプロセスである。プロトタイプ=試作品を作るという発想は以前から企業の中でも存在し、開発の段階において、実際に多く行われてきた。しかし、山中氏の提案はデザイナーによるプロトタイプ作成への介入である。今まで、製品の技術的面は試作品を作ることで実験・検証されてきた。
しかし、ここに「デザイン」や「美」の視点を取り入れた実証を行うことによって、そのモノのトータルな姿が一般にどのような反
響を得るのかを検証することができるというわけだ。こうした取り組みを通して、工学的・デザイン的ものづくりのあり方に迫っていく。
キーワード/「プロトタイピング」「人間工学」「機能性+美」
Ⅶ 松川昌平氏/無限建築
建築に時間的な無限を与えるというコンセプトのもとに、建物の永続性を保つための方法論と実践事例を解説する。その中で、建物の「代謝システム」をデザインする「メタボリズム」を取り上げ、その可能性と問題点を考察する。そして、認識と実践のプロセスにおける「かたち」「かた」「か」の関係性を通して、建築デザインにおける自然・人間・コンピューターの介在のあり方を提案し、無限建築を考える。
キーワード/「永続性」「メタボリズム」「アルゴリズム建築」
Ⅷ 松本文夫氏/建築圧縮講義
建築家である松本文夫氏が、「建築」における様々なデータを、集積・アーカイブ化した「圧縮講義」を通して、建築デザインの全体像を考察・分析していく。建築を、歴史・言語・都市様相・工学・デザイン・数学・情報学といったあらゆる視点から眺め、人類と建築物との関係性を解き、着眼点・問題意識を深めていく。
キーワード/「アーカイブ」「多角度視点」「問題意識」
Ⅸ 織咲誠氏/知覚と身体性のデザイン
モノが世界に果たせる可能性を、独自の「アート」と「設計」の方法論から述べていく。「少ないものでより多く」というシンプルさと機能性の融合によるものづくりや、「ラインワークス」による、線や構造からモノの本質を見極めることでデザイン性を高めるものくりの実践を解説する。ここから、彼独自の視点と、普遍性とをリンクさせたデザインへの考察を行う。
キーワード/「マイナスのデザイン」「造形的表現」「ラインワークス」
毎回、音楽・デザイン・アート等の領域で活躍する様々なゲストスピーカーを呼び、講演を行う授業。


No comments:
Post a Comment